カントリージェントルマンが愛した女性とは
- Country Gentleman

- 2018年12月30日
- 読了時間: 10分
更新日:2021年9月20日
今回は当ブランドが大きく影響を受けている、本物のカントリージェントルマンであった白洲次郎さんの愛した女性について、お話をしたいと思います。

https://buaiso.com/about_buaiso/jiro.html
おそらく多くの方はご存知ないお話かと思いますが。。
しかしそれでも、自分の憧れの人たちについてお話しできることは自分としては楽しく、また自らを省みる機会にもなると思っています。
本物のイギリスを知り、本物の紳士を知り、ご自身も本物のカントリージェントルマンであった白洲次郎さんが愛した女性とは、一体どんな方だったのか。
数々のエピソードと、多分に含まれた私の独断と偏見とを織り交ぜながら、お話しをしていきたいと思います。
本物のカントリージェントルマン、白洲次郎
白洲次郎さんについては、すでにこちらの記事(カントリージェントルマンとは)にて詳しくお話しさせていただいていますので、お手すきの際にでもご一読いただければ幸いです。

https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/archives/09/0102_shirasu/
ちなみにお時間がない方のために彼の略歴をまとめますと、
・1902年2月17日生まれ、大富豪の次男として誕生
・イギリスのケンブリッジ大学に留学
・帰国後、白洲正子(樺山正子)と結婚
・英語力を生かし新聞社などで働く
・徐々に政治に携わる人達と交流を深める
・第二次世界大戦敗戦後、連合軍の占領に対して日本を守るために奔走
・貿易庁の長官や東北電力の会長など要職を歴任し、日本の近代化に大きく貢献
という、略歴だけを見てもインパクトのある偉人です。
私が彼に引かれたのはその経歴ももちろんですが、彼の紳士然たる生き様でした。
「立場が上の人でも間違ったことをすれば平気で正論で立ち向かい、立場が下の人にはとにかく優しく接する」、「周りに持ち上げられ様々な要職を歴任しながらも、自分の仕事を終えたとみれば即座にその座を明け渡す」など、”風の男”と評されることもある彼ですが、その評価は言い得て妙であると感じます。
また、彼の人生を評する上でよく使われる表現として、「プリンシプル(原理・原則)を貫き通した人生」という言葉があります。
彼自身、”プリンシプルを持って生きれば、人生に迷うことはない”とも語っており、生きる上で全ての行動にはプリンシプル(物事の原理・原則)がなければいけないと、常々言っていたそうです。
彼のシビれるエピソードはまだまだ星の数ほどあり、正直今回もそれら一つ一つを紹介したい衝動に駆られるほどに彼の生き様はカッコいいのですが。。今回は彼の愛した女性、つまりご夫人であった白洲正子さんにスポットライトを当てるべく、泣く泣く次のお話へと移ります。
白洲正子とはどんな女性だったか
では、白洲次郎さんの奥様であった白洲正子さんとはどのような女性だったのでしょうか。

https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/archives/09/0102_shirasu/
簡単ではありますがまとめてみますと、
・1910年1月7日生まれ、祖父は樺山資紀(薩摩藩出身の伯爵で警視総監、海軍大臣など要職を歴任。)
・アメリカのハートリッジ・スクールに留学
・能、骨董、文学など幅広い分野で深い見識を持つ
・日本の美というものに独自の見方を持っていた
・様々な異名を持ち、「稀代の目利き」「韋駄天お正」などと呼ばれていた
・幼少より能を習い当時女性で初めて能の舞台に上がった(14歳)
・彼女の独自の見識に魅せられたファンも多く、白洲次郎が人気になるきっかけは彼女でもあった
白洲次郎さんについては、市場に出回っている本はほとんど持っていると思いますが、白洲正子さんの本もまた味わい深い作品が多くあります。(白洲夫妻を客観的に評している牧山桂子さんと牧山圭男さんの著書は、より彼らの人となりが活き活きと書かれており、私のとても好きな作品たちです。)
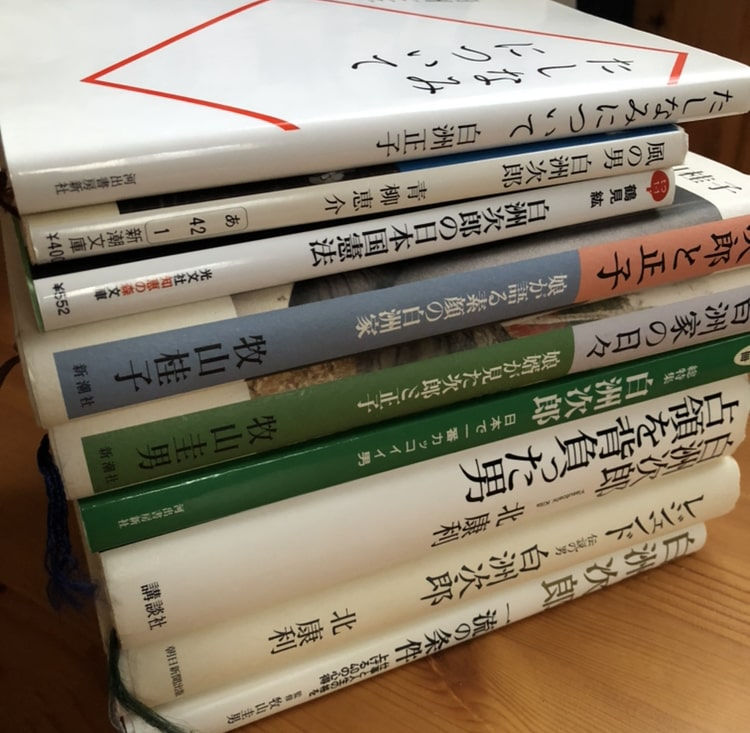
(写真は一部です)
さて、白洲正子さんはいくつもの著書がありますが、特におすすめなのが「たしなみについて」(雄鶏社新書 1948/河出書房新社 2013(改訂新書判)、河出文庫 2017)です。彼女独自の視点で、人間とは・日本人とは・国際人とはかくあるべしといったお手本のような立ち居振る舞い、考え方が綴られています。
またその他にも何冊か彼女に関する本を読むと、正子さんがどのような方であったのかおぼろげながらイメージすることができてきました。
特に強く感じたこととして、彼女は「自らの興味のあることに対して妥協することなく突き進む」という、ある意味彼女のプリンシプル(原理・原則)に突き動かされていたことが分かります。
白洲夫妻の長女・桂子さんの夫の牧山圭男さんが紹介している、こんなエピソードがあります。
”今思えば、桂子と付き合い始めて白洲のうちに遊びに行くと、ご飯の前にジントニックを飲むのも初めてだったけれど、なんだか薄汚いメシ茶碗や皿が出てきて、変な家だなとは思っていたが、それが古染付であったり、古伊万里の皿であったのだ。”
”その後何年かして(中略)売り場を見て回っていると、ガラスケースの中に、日頃正子が土瓶から無造作に番茶を注いでいる蕎麦手のざっくりした筒茶碗と同じものが納めてあるではないか。びっくりして値札を見ると、一個七十万円と書いてある”
(出典:牧山圭男 白洲家の日々 娘婿が見た次郎と正子)
つまり正子は、骨董を飾っておいて眺めるだけのものではなく、いくら高価なものでも”実際に使うこと”に重きを置いていたことがわかります。
これは娘の桂子さんが
”母は、高い品でも使わなければ意味がないと言っていました”
(出典:牧山桂子著 次郎と正子 娘が語る素顔の白洲家)
と話していることからも、意識的にそれを行なっていたことがわかります。
高価なものでも飾って眺めているだけでは、作り手の意図や想い、そしてその骨董品が持つ真の価値など分かる筈が無い。正子さんはそんなふうに考えていたのでは無いかと思うのです。
骨董品≒ヴィンテージ

https://buaiso.com/homestead/
骨董品はヴィンテージと同じものであるなどと言うと正子さんからひどくお叱りを受けそうですが、その物が持つ魅力によって「時の審査」をくぐり抜け、現代にまで置き捨てられることもなく受け継がれてきたヴィンテージ物には、ある種独特の”品格”や”貫禄”を感じられると私は考えているのですが、正子さんはそれをより具体的な手触りのある言葉に置き換えていらっしゃいます。
”この頃は雑誌の編集者たちが、どうすれば骨董が分かるようになるんですか、なんて聞いてくる(中略)ワクワクしたこともないくせに、骨董とは何事か。物とも人間と同じように付き合わなくちゃ”
”向こう(物)から話しかけてきたら本物よ”
(出典:牧山圭男 白洲家の日々 娘婿が見た次郎と正子)
いずれも「本当に価値のあるもの」を見分ける上で至言と言えるほどに感銘を受けた言葉です。また、正子さんはこの他にも
”高価なものが良い訳でもなく、自分のレベルで気に入った物を買って、満ち足りた時を過ごすことが大切。それで壊れてしまったらそれでいいじゃないの。それだけ身についたと思えば、美味しいものを食べるのと一緒よ”とも。
物をただの「モノ」としてでは無く、「対話の対象」と捉えていたからこそたどり着いた、目利きの頂点からの眺めは、私のような凡人こそ参考とすべきと常々感じています。
ヴィンテージと言えるもの、言えないもの
強引ではありますがヴィンテージも「対話の対象」と捉えれば、それ以外のものと分けることはおそらく容易になることでしょう。

https://buaiso.com/homestead/
例えば中国の現代の工場で量産されたものと、90年前に職人の手で一つ一つ手作りされてきたものとの間には、対話できる事柄に圧倒的な量の差が生まれてきます。
後者であれば、例えば「90年前であれば大体1930年頃。ヨーロッパではアール・デコの揺り返しとしてのアール・ヌーヴォーの復興の動きが芽生え始め、当時の職人もその機運に乗っかり絢爛豪華なデザインをその手に取り戻そうとしていた」などの背景に想いを巡らせながら、
(正子さんから言えば、それは対話ではなくただの知識だ!と叱られそうですが。。)
何よりその物が時を超えて身につけてきた品格・貫禄のようなものを感じ取れるだけでなく、「俺をみているんだろ」という声までも、聞こえてきそうな気がします。
しかしそのように対話のできるヴィンテージの物を、ガラスケースに入れて飾り、眺めているだけでは本当の価値は知り得ないであろうことも、正子さんの至言から感じ取ることができます。
「デザイナーや職人は、どのような意図を持ってこのような手触りの物を作ったのか」、「この器のフチはなぜこのように唇に当たるのか」、「なぜこの部分にこのデザインがくるのか」、「このラインは何を表し、この色は何を訴えているのか」
これらの対話は実際に手で触れ、使ってみることでしか感じ取ることのできない対話です。
だからこそ、稀代の目利きと称された白洲正子さんは、それがどれだけ高価なものであったとしても「使うこと」に重きを置いたのであろうと思うのです。
現在日本でも、ヴィンテージのアクセサリーやその他様々なものを買い求める方たちが、以前にも増して多くなってきているように思います。
しかし「なんとなく古いしカッコ良いよね」、「古っぽい見た目だから雰囲気が良いね」そんな楽しみ方も確かにあるとは思います。しかしそれだけでは、そのものの本当の価値を捉えきれているとは言えないと思うのです。
「これはなぜ現代の自分の手に渡るまで、捨てられることもなく受け継がれてきたのか」、「それだけの価値があるとみられたのであれば、これが制作された背景にはどんな時代の流れがあったのか」、「デザイナー・職人はどのような想いでこれを生み出したのか」
これらも一段上の接し方であるとは思いますが、本当のところ自分の心とその物とが、どこかで通じ合うような感覚を覚えることがあったなら、そんな瞬間を私も夢見ています。
そんな対話を楽しむことも、本来のヴィンテージの楽しみ方であるように思います。
カントリージェントルマンと、その愛した女性
さて、そんな超一流同士の夫婦であった白洲夫妻ですが、その夫婦仲はどのようなものだったのでしょうか。

https://buaiso.com/about_buaiso/masako.html
娘婿である牧山圭男さんがこれまた的確な表現でお二人の関係を言い表しています。
”次郎・正子夫婦は、プリンシプル(原則)とコモンセンス(良識)の、あるレベルを共有した大きな柵の中で、それぞれお互いをおおらかに放し飼いにしているように、私には見えた”
(出典:牧山圭男 白洲家の日々 娘婿が見た次郎と正子)
と話しています。
白洲次郎さんも夫婦仲をよく保つ秘訣を尋ねられた際には、”なるべく一緒にいないことだよ”と言っていたことからも、この表現がピッタリ当てはまっていたことがわかります。
相手に依存するのではなく、また「男性だから」「女性だから」というような決まり切った分類で物事を判別するのではなく、原則と良識を高いレベルで備えた男女というのは、夫婦になった後でもそれぞれ1人の人間として自立したまま、お互いを尊重し支え合うことができるのだと、白洲夫妻の関係は私たちに教えてくれているような気がします。
また白洲次郎さんはハンサムな紳士で長身・お金もあったことから女性にモテないわけはなかったのですが、白洲正子さんは”浮気は一度もなかった”と言っていたほどの愛妻家でした。
ちなみに白洲次郎さん自身も
”家族が面白くないから男は外で遊ぶのだろうが、それでおめかけさんを囲ったら、またそこから逃げ出して、別の家庭を作らなきゃいけない。”
”僕はそんな無駄なことはしないよ。牛乳一杯飲むだけのために牛一頭買う馬鹿がどこにいる”
(出典:牧山圭男 白洲家の日々 娘婿が見た次郎と正子)
と言っていたそうです。
お互いに独立した人間でありながらも、男女として好意を寄せ合う二人の関係には、学ぶところが多くあるように思います。
白洲夫妻から学び取る事柄
物の本来の価値を知るための対話、独立した2人の人間が尊重しあう理想の夫婦関係。
まだまだ自分には彼らの全てを理解することなど到底無理ですが、そんな稀有な存在がいたこと、そしてそんな高みに到達した人たちが語ることを少しづつでも咀嚼していくことで、自分も一人の人間として少しでも成長していけたら。
当ブランド、Country Gentlemanの活動を通してそれを実現できるように、私は今日も新たなヴィンテージとの出会いを楽しんでいます。
ヴィンテージを愛する方々に、嬉しい驚きをお届けできるように日々精進して行こうと思っております。




コメント